
���̗l�ȑ�O�ғI�ڐ��ł���Ȃ��牽������ς߂����A���Ƃ�������s����s���Ŏn�܂��i��1986�N���s/����C�u�ۂ������j�v�i�k�~���[�j�ł���܂��B
���̓Ƒn�I���O�q�I�ȍ�ƁE��i�𐔑������ɑ���o���Ă����G���u�K���v�ɂĖ���ƂƂ��ăf�r���[���ʂ�������C���������Z�ҏW�u�~�L�v�i�k�~���[�j�A�����Łu���[�J�����̌ߌ�v�i�ѓ��j�A�u���w����C�����i�WII�v�i�k�~���[�j�ƒP�s�{���o�ł��A�l��ڂƂ��Ĕ��\�����̂����S�������낵���u�ۂ������j�v�Ȃ̂ł��B
���̍�i�����\���ꂽ���A�����������Ă��Ȃ��������������łȂ�܂���B�ǂ�قǏՌ��ł����������I�I

���̖���́A����ł����Ė���ł͂Ȃ��A�܂��ď����ł��f��ł����y�ł��Ȃ��A�ł͉����Ɩ����ƁA��͂薟��Ȃ̂ł��B
����ł����������Ȃ��\�����ӂ��ƌ���A����炪���Ƃ����ȗ҂����Ô��������Ď��B��U�f����ƁA�C���t����i�̒��֝����Ă܂��Ă�����̂ł�����A�����͍������ǂ�ł����̂�����Ƃ����܂ł����Ƃ����ɋ����̂��A�B���͌ЂƂȂ蔻�f���t���Ȃ��Ȃ��Ă��܂���ł��B
�����������̂͂�͂�h�������낵�h�Ȃ�ł͂̓Ɠ��ȃ��Y�����ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B�ܘ_���ꂪ��������̂���Ǝ��g�̊��o�������Ă����Ȃ̂ł����A�������Ȃ���G���A�ڂł������炱�������ɐS�n�̗ǂ��s����ȃ��Y���͐��܂�Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���Y���������鎖�Ȃ���A���Ќ����Ă��������̂����쎁�̕q�����ł���܂��B���܂ŃR���g���X�g��������������Ői�s���Ă����͂����u�ԁA�L���ɕς���Ă��܂��Ƃ�����������킯�ł��B��������y�[�W�̂݁B��ˎ������������̖���͋L�����A����͋L���ł���A�ƌ��������L���_�͗L���Șb�ł����A����ɂ��Ă������܂ł��܂�������搶�I�Ƌ���ł��܂����̏Ռ��������̎��͎܂����B�����ǂ݂Ȃ��炻�����ɏo���Ă��܂��܂����B����Ȏ����o����̂����h�������낵�h�Ȃ�ł͂ł���A���ꂪ���Ɠ��̃��Y���������o���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���ƁA���̗����ł͒ǂ����Ȃ���i���̂̃o�C�^���e�B�Ɉ��|�������Ă��܂���ł��B
�u���̓N���[�����B�����Ĕ߂����t���b�J�[���B�v
�X�Ɋ�����̂́A�����ɍ�Ғ��M�ɂ�邠�Ƃ��������鎖�ł��B���Ƃ����t�@���̎��ɂƂ��Ă͋я�Ԃ�Y����Ƃ͂������������Ǝv������ł��B�����Ă��̂��Ƃ�������͂�A��i�ɍŌ�̉Ԃ�Y���Ă����ł����牽�����Ƃ��Ă��{���ɖ��������i�ł��葱����̂ł��B
���̍�i����Ɏ�����łɂ́A���Ƃǂ��炪�߂����̂�����ׂ������Ă݂܂��H
��������̏��i�͕��y�ŁF����450���ƂȂ��Ă���܂��B�����ł���x�ł������琶�Ō��Ă݂������̂ł�...�B
������̏��i��5��3���i���j����̔����܂��B
���O�̎��u���A�d�b�ʔ̓��͂��ł��܂���̂ł��������������B
(�S�� ����)
�����ӓ_
�f�ڂ̏�̔����̏ꍇ
- �f�ڏ��i�ɂ��Ă̂��₢���킹��(�w�肪����ꍇ�͏�L�R�����g���ɋL���Ă���܂��̂ł��m�F��������)�J�X30���ォ��̎�t�ƂȂ��Ă���܂��B�e�X�̊J�X���Ԃ́A�X����ɂĂ��m�F���������B
- �f�ڂ̏��i�͓X���ł��̔����邽�ߔ�����ꍇ���������܂��B
- ���i�̒T���́A��p�̒T���t�H�[���������p���������B
�f�ڂ̏������̏ꍇ
- �f�ڂ̔��承�i�͏��i��ԁA�ɂɂ���ė\���Ȃ��ϓ����܂��B
����X �V���ʔ̏��i
���₢���킹 (�c�Ǝ���:12:00�`20:00)
�܂炯����X(�ڂ����X�ܒn�}�͂�����)
��164-0001 �����s����撆��5-52-15
TEL:03-3228-0007 / e-mail:nakano@mandarake.co.jp
��164-0001 �����s����撆��5-52-15
TEL:03-3228-0007 / e-mail:nakano@mandarake.co.jp



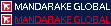



 ���̃y�[�W�̐擪��
���̃y�[�W�̐擪��

